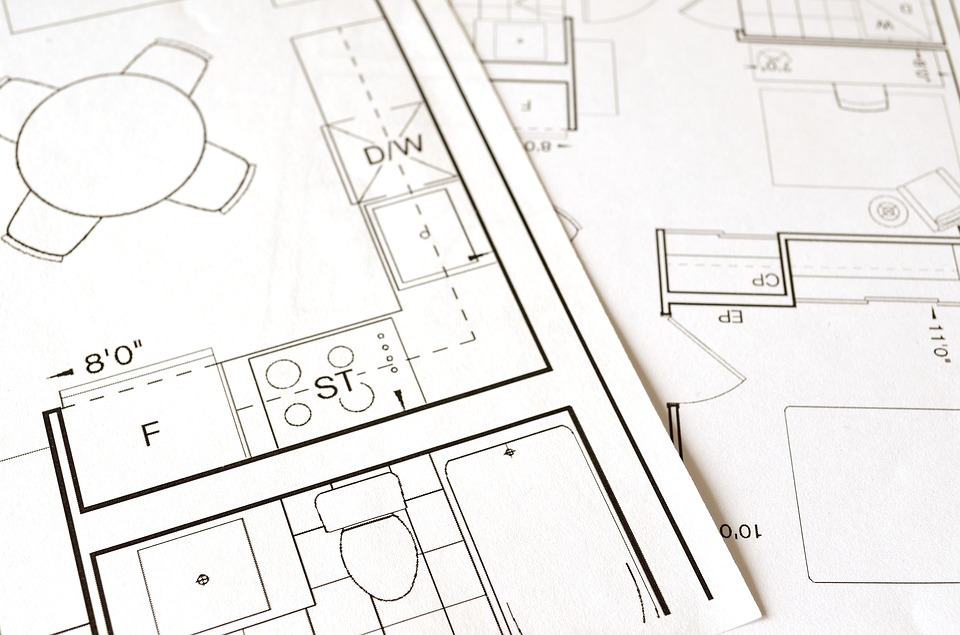害に強い家の特徴と自分でできる5つの対策
今年も、梅雨が明けたにも関わらず、各地で豪雨が頻発し、水害が発生しています。
洪水や浸水といった水害も決して「対岸の水害」ではありません。
家を建てる際には、水害による被害をどう避けるかといったことを念頭に置いておくのが、非常に大切です。
河川が近いとか土地が低めであるといった水害発生の危険性があれば、家を建てる際にしっかりと対策を講じておく必要があります。
今回は、水害に強い家の特徴をご紹介し、自分でできる5つの水害対策を伝授いたしましょう。
1.家を建てる前の水害対策
ひと口に水害といっても、その態様は様々です。
台風がもたらす豪雨など、ある程度予想ができる水害から、近年頻発している都市部でのゲリラ豪雨被害、さらには山間部での鉄砲水とその影響による土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)といったものまであります。
そして、その被害も家の流失、床上・床下浸水、排水の逆流など様々ですので、それぞれの事態に見合った対策を立てる必要があります。
異常気象が通常となった感のある昨今ですが、水害から命と生活を守るという命題は不変です。
大切な家に、ずっと住み続けるためにも、家を建てる前から水害対策をとっておきましょう。
1-1. ハザードマップの確認
ハザードマップとは、各自治体が発表している災害予測図のことです。
水害のほか、地震や土砂災害、噴火など、今後発生が予測される自然災害に関して、被害範囲やや程度、避難経路、避難場所などを地図上に記しています。
住みたいと思った土地が決まれば、まずは、その土地の自治体が出しているハザードマップを確認して災害危険度を理解しておきましょう。
各自治体によってハザードマップが発表されていますので、お住まいになる予定地域の自治体ホームページなどからプリントして、いつでも取り出せる場所においておきたいものです。
もちろん、ハザードマップで被害が想定されていても、それだけを理由に家を建ててはならない、ということではありませんし、反対に、ハザードマップで特に浸水のリスクがないとされているエリアでも、浸水被害は起こり得ます。
例えば、高台でも、すり鉢状の地形になっているところにピンポイントに雨が降れば浸水リスクは高まります。
つまり、特に水害に関しては、100%安全と言いきれるような土地は、日本には存在しない、と言って良いのですから。
重要なのは、予想される危険度に見合った建て方をしているかどうかなのです。
水害、特に床上浸水の被害を最小限に抑えるためには、土地をかさ上げしたり、基礎部分を高くして周辺より家自体を高くしたり、周囲を塀で囲んだり、家自体を防水性のある建材で囲んだりするのが、浸水に対して有効だと言われています。
ハザードマップを確認した後は、具体的な工法を見ていきましょう。
1-2. 盛り土
盛り土は、代表的な水害対策です。
敷地全体にまんべんなく土を盛り、周囲より床を高くすることにより、人工的に海抜を高くしてしまうわけです。
水は高所から低所へ流れるという性質がありますから、敷地を高くすれば、家全体を水害、特に洪水や浸水から守ることができます。
周囲の家や道が、あなたの家が立つ土地よりも、海抜的に高くなっている場合には、是非ともやっておくべき工事なのです。
ただ、住宅地では、隣家の日当たりを妨げないよう屋根の高度制限がありますので、地番のかさ上げをするにも限界があります。
また、河川に近い場所は、ほとんどの場合、地盤が軟弱な低地です。
盛り土はそれ自体の自重が重いので、軟弱地盤では、逆に沈下の原因となってしまう場合もあります。
盛り土をして家を建てる時は、その土地の特性と周囲の状況をよく考慮して着工しましょう。
1-3. 高床構造
次に、家を高床構造にする、という方法があります。
基礎部分を、通常よりも高くし、周囲の家よりも家自体を高く位置させるのです。
家を建てる際にはまずコンクリートなどで基礎を作りますが、この基礎を通常よりも高く形成するすることによって、床上浸水を防ぐことが出来ます。
ただ、高床構造の場合この場合、床上浸水は防げても、床下浸水の可能性は十分ありますので、床下を排水しやすい構造にしておかなくてはなりません。
ちなみに、高床構造は、水害対策以外にも、湿気対策にも効果を発揮します。
そのため現在も熱帯地方の住居は高床式が多いですし、多くの宝物を所蔵している日本の神社建築、古代の倉庫などにも採用されています。
1-4. ピロティ構造
一階部分に居住空間を作らず、柱だけの空間にしてガレージなどにして、2階以上を居住スペースにする建築方式があります。
一般にピロティ構造と呼ばれています。
フランス語のPilotis(杭)に由来する名称です。
東日本大震災の際、津波で多くの建物が流されましたが、ピロティ構造の建物は外壁がないために津波のエネルギーを受けず、流されにくかったと言われています。
逆に、耐震設計上、その柱部分が弱点となるため、阪神・淡路大震災ではこのピロティ構造の建物に崩壊が集中し、被害が増大したとも言われています。
ピロティ構造の建物の設計では、耐震性を損なわないため、柱を相当頑丈に作らなければなりません。
1-5. 家を囲む
家の周囲を浸水防止塀で囲むことにより、敷地外からの浸水を防ぐ方法です。
低地の住宅地などは、自治体の道水路整備工事のみでは浸水被害を食い止めることができないため、浸水防止塀設置補助金を出す自治体も多くあります。
1-6.建物防水
家自体を、防水性のある建材で囲み、浸水被害を防ぐ方法です。
洪水など大規模災害に見舞われなくても、日々の風雨や紫外線により、建材は経年劣化していきます。
建物自体を防水性のある建材で囲めば、突発的な浸水を防ぐのみならず、長期的な家の維持にもつながります。
2.自分でできる5つの対策
以上、家を建てる前の水害対策を見てみました。
ただ、いずれも大規模な工事が必要となりますし、そもそも、既にある家にお住まいの方には、経済的にもかなりハードルの高い対策となってしまいます。
そこで、次は、ご自分でできる水害対策を5つ、ご紹介しましょう。
2-1. 土のう
土のうとは、布袋に土砂を詰めたものです。土のうを積んで、水や土砂の流れを止め、家屋への浸水を防止するので、水深の浅い初期段階や小規模な水害時にには、非常に有効な対策と言えます。
実は、土のうは各自治体が無料で設置しており、水害発生時には無償提供されます。
水害被害を直接受ける前に、ご自分の済む地域の土のう配布場所を確認しておきましょう。
また、市販の吸水性土のうなどもあります。
水害時に、わざわざ配布場所まで取りに行くのは非常に危険ですので、市販の土のうをご自宅に常備しておくのも良いでしょう。
特に、水害被害を受けやすい半地下・地下に玄関や駐車場、居室がある家にお住いなら、すぐにでも、自治体に問い合わせたり、自分で調達しておいたほうが良いでしょう。
2-2. 止水板
家の出入り口に、長めの板などを設置して、先ほど触れた土のうや水のうなどで固定して、浸水を防ぎます。板がない場合は、テーブル・ボード・タンス・ロッカー・畳などで代用することも可能です。
先ほど触れた水のうを段ボール箱に詰めて、積み重ねれば、立派に止水効果を発揮します。
市販の止水板を購入した際には、補助金を出してくれる自治体もありますので、お住いの自治体のホームページなどをチェックしてみましょう。
2-3. 排水溝のチェック
ゲリラ豪雨など、突発的で激しい水害時は、トイレや浴室、さらには洗濯機などの排水溝から汚水が逆流する「排水溝逆流浸水」が発生し、室内から泥水が噴き出す恐れがあります。
この排水溝逆流浸水への対策としては、「水のう」が役立ちます。
45リットル程度のビニール袋を二枚重ねにして、20リットルほど水を入れます。
袋を押さえて、中の空気を抜いて、口の部分をしっかり縛ります。
水害発生時に、この水のうをトイレ便器の中、浴室・浴槽・洗濯機の排水溝などの上に載せておけば、逆流浸水を防ぐことが出来ます。
また、水のうを複数個作り、段ボール箱に詰めれば、先ほど触れた土のうの代替品としても役立ちます。
無用と思える段ボール箱やビニール袋も、いざという時のためにストックしておくのも良いでしょう。
2-4.自前のハザードマップ
ここでも、先ほどご紹介したハザードマップが有効です。
さきほどご紹介した自治体のハザードマップは、被害を受ける地域を示すものですので、実際に水害が起きてしまった場合に十分役立つものではありません。
そこで、水害が起きてしまった後のために、自前のハザードマップを用意しておくことをおすすめします。
水害が起きてしまい、避難が必要になった時、避難経路上のマンホールや小川、側溝などの危険箇所をマップ上に示しておきましょう。
濁流で冠水した場合、危険箇所が見えなくなります。
避難途上にふたの外れたマンホールや側溝に落ちて犠牲となるケースも非常に多いのです。
ですので、平常時でも雨が降ったら、水の流れる方向や川の濁り具合など、こまめに周囲の状況を確認しておきましょう。
そうすれば、水害に発展するような異常を察知でき、早期の自主避難も行うことが出来ます。
また、平常の降雨時に、あらかじめ避難場所、避難経路を実地で歩いてみる必要もあります。
避難場所を探すのに手間取って、甚大な被害を蒙ってしまっては元も子もありません。
ただ、注意点もあります。
大きな河川の近くで氾濫や洪水で家が流される恐れががある場合は、
高台や近くの鉄筋コンクリート造りの3階以上に避難するのが安全ですが、都会のゲリラ豪雨時は、遠くの避難場所を目指すよりも、隣近所の二階以上に避難させてもらうほうが安全です。
また、たとえ避難勧告が発令されても、目視困難な夜間の場合や、濁流に包囲されている時は、
そのまま自宅待機が良い場合もありますので、冷静な判断の上、行動するようにしましょう。
例えば、家の裏面が傾斜地でしたら、土砂災害の恐れがあります。
直ちに安全な場所への「立ち退き避難」が必要となりますが、夜間であったり、既に周囲に水が溢れている状態でしたら、斜面から離れた2階の部屋に避難する「屋内安全確保」を選択すべきです。
また、川の流域に家があれば、浸水や流失の危険性があるので、安全な避難場所へ立ち退き避難をしましょう。
いずれにせよ、自治体や自前のハザードマップのみを過信せず、気象情報や周囲の状況に注意して、水害の危険があるようなら、明るいうちの避難を心がけるようにしましょう。
早期避難にまさる避難方法はない、と言っても良いくらいです。
2-5.非常用品備蓄
大規模水害時には、水道、電気、ガスなどが止まり、道路が寸断される可能性もあります。
ライフライン途絶を想定し水、食料、日用品、カセットコンロ、カセットボンベ、予備電池、防水懐中電灯、携帯電話充電器、医薬品、ランタンなど、最低でも一週間は暮らせる備蓄があれば安心でしょう。
これらについては、季節の変わり目を目安にして、故障がないかなど定期的なメンテナンスを心がけるようにしましょう。
そして、いつでも持ち運びができるよう、まとめて一箇所に保管しておきましょう。
荷物は最小限にし、極力両手を開けて避難します。
近年は、水に浮くリュックなども市販されていますので、そこに入れておけば浸水時にも運びやすくなります。
3. まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここまで述べた方法は、あくまでも代表的な事例です。
実際の水害発生時は、どんな想定外の事態が起こるか誰にも分かりません。
常に、情報収集に努め、お住いの地域に合った災害対応力を維持しておくのが、絶対に必要でしょう。
また、周囲の親しい人々と、シミュレーションのつもりで、避難訓練などしておくのも良いかもしれませんね。
いずれにせよ、日頃からの自助努力と互助努力が、緊急時にはモノを言います。
皆さんの命と生活を守るためにも、このことを常に念頭に置いておきましょう。